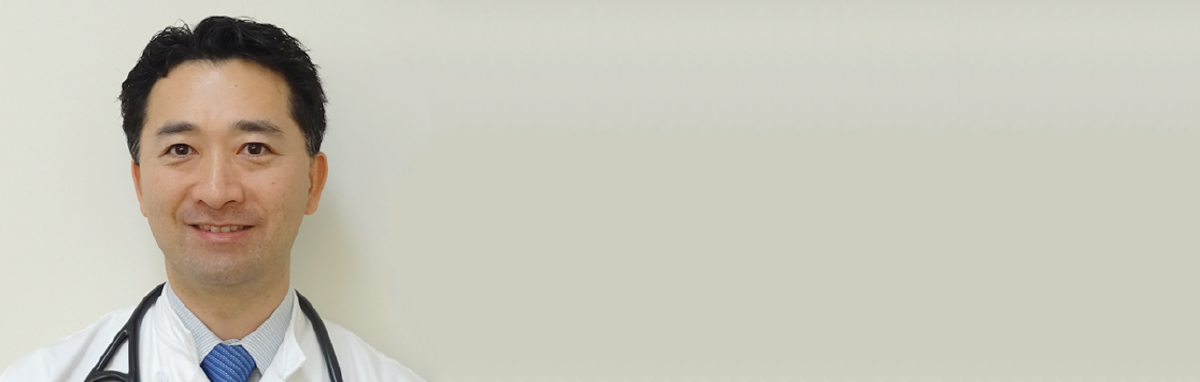新年のご挨拶
医療法人 医仁会 理事長
小林 豊

我々からすると「ようやく」ではあるが、日本の救急病院の恒常的な赤字経営についてマスコミが取り上げ、国民の多くがこの窮状について認識した。なぜ赤字になっていったのか。それは人件費の上昇・光熱費の上昇・医療材料費の上昇を中心とした経費の止まらぬ高騰に対して、2016年の診療報酬改定からずっと事実上のマイナス改定によって、売り上げと経費の逆転が起きてきたためである。医療は高度化し、同じ医療を提供するのに材料費が嵩み、高齢化社会によって必要な医療を必要とする国民が増える一方のために、本来の国民全体の医療費が増えて当然なところ、頭打ちにされてきたことが背景にある。
高齢化社会に伴って、2015年に41兆円だった日本全体の医療費は2024年には48兆円と2割も増えている。2015年度の国の一般会計税収(税収総額)は、56兆円であり、2024年の税収総額が78兆円であるが、税収総額のうち医療費の国費負担は2015年・2024年ともに約10兆円であった。これを計算すると、2015年の税収総額の17.8%が医療費に充てられていたものが、2024年では12.8%が医療費に充てられた、ということになる。つまりこの10年で国の税収において17.8%使われていたものが12.8%しか使われなくなった、という読み方ができる。医療費が適正に充てられていない、ということはこれだけでもわかる。もし、医療費が10%増えたとしたら、医療費の総額は61.6兆円となり、税金としての国費負担も単純に1割増えたとしたら11兆円になる。これを2024年の税収総額に当てはめると、医療費の国費負担は14.1%に過ぎない。つまり2015年の国費負担率にも有意に満たないのである。
日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会、日本慢性期医療協会、全国自治体病院協議会、の6団体は「診療報酬の10%を超えるプラス改定が必要」と緊急要望を出した。これは全国の病院が存続するために必要な診療報酬の理論値である。しかしながら、報じられた2026年6月の診療報酬改定は「プラス3.09%」であった。1996年以来の3%台のプラス改定らしい。この改訂により日本の多くの病院の延命は得られたが、救命には至らない。現在の診療報酬改定は潰れる病院と生き残る病院を篩にかけられているように感じる。延命期間のうちにこのどちらに入るかを選別されるような流れである。
では、当院はどちらに入るのか。この延命期間にいかに黒字化するかが求められている。「断らない医療」を1980年の創業以来堅持してきた当院は、年間3,000件を超える救急搬送件数を対応する医療機関として社会に貢献し続けるために、経営改善が急務というわけである。2024年には診療報酬の包括評価制度(DPC)に参入し、2025年には病棟再編として急性期医療を担う一般病棟の大部屋を1病棟から2病棟に増やした。本年は美容医療センターの開設を1月に迎え、この調子で看護師の増員を進め、年々増えている常勤医師をさらに増員することにより理想的な医療の提供を目指している。
2025年は「直美(ちょくび)」という言葉が広まった。若い医師が初期研修の2年を終わって、目指す各専門診療科の専攻医としての研修をして医師として一人前を目指していくのが通常であるが、この専攻医としての研修を受けずに美容医療に進むことである。「一人前の医師になるのに10年かかる」と言われて医師になったが、10年では到底一人前になんてなれないことは実感している。そんな中で一人前の医師になることをやめて美容医療に身を投げる、ということは医師としての基本的な成長を捨てることになる。当然の如く、一部の美容クリニックでは様々な医療事故が起きているのが現状である。当院は総合病院として、この美容医療をもっと安心安全なものとして提供できないか、という命題にチャレンジすることにした。美容医療のメッカと言われる韓国の薬品会社とタイアップして「きちんとした」「安心安全な」美容医療を展開するべく準備を進めてきた。美容専門のクリニックよりこれをさらに安価に提供することにした。美容医療は見てくれだけを改善するものなのであろうか。我々は、若返ることで色々なことに対する意欲が生まれ、ストレスが減るのであれば、これは疾病予防にも繋がり、健康寿命をも伸ばすのではないか、と考えている。しかも自費診療。つまり冒頭で述べた医療費を食わないのである。医療費を食わないばかりか、疾病予防にまで繋がれば健康な中高年が増え、医療費削減にまで寄与すれば、と考えを馳せるのが保険診療を中心に勤しんできた救急病院の美容医療への淡い期待なのである。
存続する救急病院は攻め続ける病院だろう。あの手この手で色々な改革改善を進め、スタッフ一同が前を向いて笑顔で働いている病院が生き残る。国が期せずか期せずしてか設けた延命期間に、存続する道を迷わず見つけ出せる病院を当院は目指して走り続ける。新年を迎え、今年が当院ならびに当法人の大きな転換のタイミングである、ということを自覚されたい。その先に「笑顔で長く働ける職場」という掲げた理想がそこにはある。